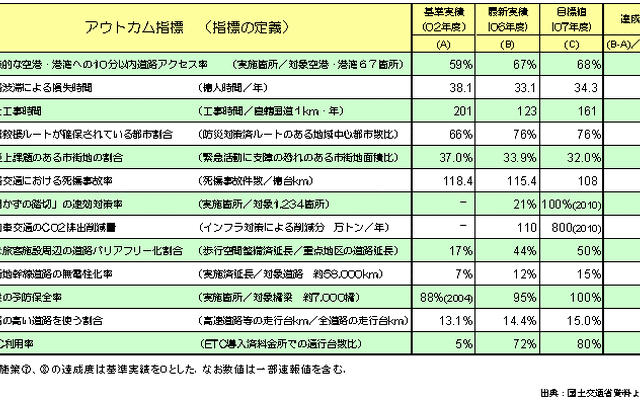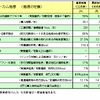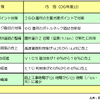CO2削減余地の大きな日本の交通事情
道路行政では、交通事故、渋滞、環境負荷の軽減などのアウトカム(成果)目標を指標化し、対策の達成度を評価している。道路交通対策のCO2削減効果に注目し、評価について考えてみたい。
国土交通省は、インフラ対策によってCO2を2010年までに800万トン削減する目標を立てている。800万トンは、運輸部門のCO2排出量の3%強に相当する大きな値だ。
これほどの削減が見込めるのは、日本の道路交通はまだ効率をアップできる余地が大きいためだ。渋滞がその典型だが、高速道路が充分に活用されていない点も大きい。また近年、日本全体の交通需要の伸びが頭打ちになってきた。交通量が増加しないことは、効率アップがそのままCO2削減につながるため、環境面では好材料だ。
◆06年度のCO2削減実績
表1の道路交通対策の主なアウトカム指標のうち、CO2の評価は「(8)自動車交通のCO2削減量」だ。目標の800万トン削減に対し、06年度の実績は110万トンとなっている。その内訳は、渋滞ポイント対策で44万トン、ボトルネック踏切の対策で10万トン、環状道路の整備で5万トン、高速道路の利用率向上で18万トンなどだ(表2)。
渋滞ポイントやボトルネック踏切の解消は、対策箇所数に応じて今後も削減が期待できる。環状道路では、07年度も圏央道と中央高速の接続や首都高速山手トンネル、名古屋の都市高速の開通があったので、さらに交通の分散が進みCO2は減るだろう。
◆評価の精度を上げるには
道路交通対策のCO2削減効果を評価するには、道路の旅行速度と交通量からCO2を計算する必要がある。燃料からの計算では、クルマの燃費性能など対策とは無関係な要因を排除できないためだ。
評価の精度向上は困難な課題だ。例えば表2のように、対策ごとに効果を積上げる方法では漏れや重複が出てしまう。路上駐車の取締り強化は06年度の大きなトピックだったが、考慮されているのだろうか。またVICS普及のような対策は、箇所別の対策と効果を区別するのが難しい。
精度向上のためには、対策の有無に関わらず、全国の道路を対象にしたCO2の増減把握が第一歩だと思う。中には増えるところもあるだろうが、「減ったところだけ出す」というのはあまり意味がない。困難な課題だが、さらなる“成果の見える化”が望まれるところである。