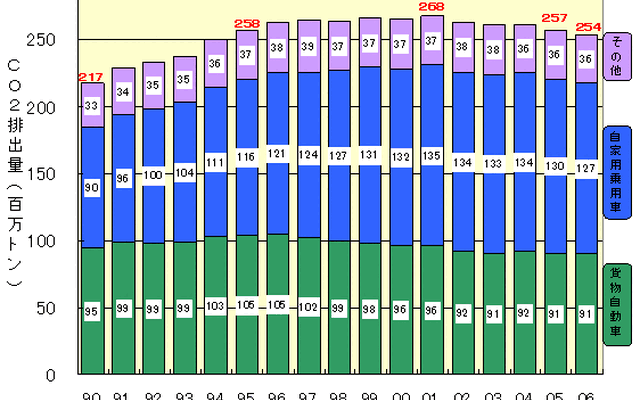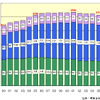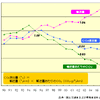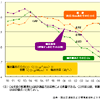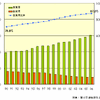トラックのCO2排出量
運輸部門のCO2排出量は、06年度は2億5400万tとピークの01年度からは1400万t減となった。旅客、貨物とも減少傾向にあるが、貨物部門ではトラック輸送の効率化や燃費改善が成果をあげている。
トラックなど貨物自動車からの排出量は、96年度の1億500万トンから06年度は9100万tに減少した。03年度以降は横ばいが続いているが、自家用乗用車の排出増が続いていた90年代後半、いち早く減少に転じたのが貨物自動車からの排出であった(図1)。
◆CO2減少の要因
貨物自動車からのCO2が減少したのはなぜだろうか。単に輸送量が減っただけなのか、それとも何らかの改善が図られたのだろうか。
まず、貨物の輸送量、CO2排出量、輸送量あたりのCO2排出量の推移を見てみよう(図2)。輸送量はほぼ一貫して増えている。他方、輸送量あたりのCO2排出量は減っており、その減少率が輸送量の増加率を上回ったことが、CO2減につながったことがわかる。
何が改善したのだろうか。輸送の効率がアップしたのか、それもとトラックの燃費が良くなったのだろうか。輸送量あたりのCO2排出量を、さらに燃費(走行1kmあたりのCO2)と輸送効率(貨物1tあたりの台数)に分解してみよう。両者とも改善しているが、特に輸送効率の改善が目につく(図3)。
◆営業用トラックへの転換
輸送効率の改善は、自家用から営業用トラックへの貨物シフトが進んだことが大きい。営業用、いわゆる緑ナンバーのトラックは、自家用より大型で積載率が高く、同じ量の貨物を運ぶ際、走行量が少なくて済むためだ。
営業用と自家用では、1台の積載容量は平均7.7tに対し1.1t、積載率も50%対25%と倍半分の開きがある(いずれも06年度値)。容量で7倍、積載率が2倍なので、営業用は14倍も効率が違うことになる。またトラック事業者がエコドライブやアイドリングストップに取組んでいることは、多くの方がご存知だと思う。
今後も営業用トラックへの貨物シフトが進めば、さらにCO2削減が期待できるのだが、既に9割近い貨物が営業用トラックによって運ばれている(図4)。自家用もゼロにはならないため、そろそろ営業用シフトは頭打ちとみなければならない。これからは、共同輸配送や重量車の燃費基準による燃費性能アップなど積載率と燃費を向上させる対策が軸となるだろう。