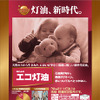日本国内を走るほとんどの車両はガソリンや軽油を使って走っている。PHVやEVが登場したとはいえ、内燃機関の効率向上も進んでおり、もうしばらくは化石燃料が自動車の主要燃料であり続けることは疑いない。
このように、ガソリンや軽油は自動車にとってなくてはならない存在でありながら、どのように研究開発されているのか、なかなか伝わってこないのも事実。そこで今回、昭和シェル石油の中央研究所で、最新の燃料研究開発の現場を取材した。
◆90年代前後のパワー戦争で一躍ブームに…フォーミュラシェル スーパーX
昔の車のフューエルリッドの裏側に「無鉛」「有鉛」「混合」などといったステッカーが貼られていたのを覚えている人もいるだろう。日本では、1975年から環境および健康問題からガソリン無鉛化が始まった。当初はオクタン価の高いガソリンが無鉛では実現できず、また古いエンジンのために有鉛ガソリンと無鉛ガソリンが併売されていた。そのため、上記のようなステッカーが必要だったわけだ。
しかし、無鉛ガソリンでも高オクタン価の開発が進み、1987年に昭和シェル石油が「フォーミュラシェル スーパーX」という無鉛ハイオクガソリンを市場に投入し、ブームの火付け役となった。
2000年代に入ってハイパワー戦争もひとまず落ち着くと同時に、環境意識の高まりにより、ガソリンも時代への対応を迫られた。そこで昭和シェルでは、エンジン内部やバルブのカーボンを除去する洗浄効果をもち、燃焼効率の劣化を防ぐ『シェルピューラ』を2002年に登場させた。
少々前置きが長くなったが、これらシェルピューラなどを初めとする燃料の研究・開発をおこなっているのが、昭和シェル石油の中央研究所である。石油会社の研究所とは、どんな研究を行っているのだろうか。
◆40年以上の歴史を持つ“油”の総合研究所
中央研究所は神奈川県愛川町の工業団地の一角にあり、敷地面積は3万8000平方メートルと広大。開所は1967年で、燃料研究の施設としてはかなりの歴史を持つ。現在は約70名の職員が日々研究に勤しんでいる。
この研究所の主な事業は、昭和シェル石油の各種燃料やオイル製品などの品質向上と新製品の開発である。重油、灯油、軽油、ガソリン、航空燃料などの各種燃料の品質・性能向上や精製など加工法についての研究をすすめているほか、自動車用および工業用の各種潤滑油、グリース類の研究・開発も行っている。
潤滑油は、自動車用であればエンジンオイルやミッションオイルなどであり、工業用では工作機械の潤滑油、旋盤などに使う冷却用潤滑油などである。グリース類は、原則として交換や補充を前提としない粘性の高いオイルだ。
長期間にわたって性能が安定しており、可動部分の保護、潤滑を目的とする。他にも、石油精製の最終段階で残るピッチを利用したアスファルトの開発も行っている。降雨でも水たまりができにくい高浸透性のアスファルトもここで研究が行われている。
◆環境対応燃料の開発も重要なテーマに
また、環境・新規ビジネスに関する研究も重要な目的である。次世代のエネルギーとして、太陽電池や水素エネルギー、EV用の充電設備、GTL(Gas to Liquids)燃料の開発・研究などを行っている。GTL燃料とは、天然ガスから作られる灯油や軽油に相当する液体燃料で、気体である天然ガスを液体にするためこの名前がついている。
ちなみに、LNGと呼ばれる液化天然ガスは、温度や圧力によって液体化させている天然ガスだが、GTLは天然ガスを化学反応によってパラフィン状(液体)に変化させたもので、常温でも液体のままである。
GTLは、天然ガス由来なので、硫黄成分が含まれないクリーンな燃料を作ることができる。そのため、排気ガスにSOxを含まず、においもきつくないといった特徴を持っている。GTL灯油は、べとつかずにおいも少ない「エコ灯油」としてすでに商品化されている。また、低SOx、低SPMの特性から、新しいディーゼルエンジンの燃料としても注目されている。中央研究所では、最寄の小田急線本厚木駅までの通勤用シャトルバスにGTL軽油を使った走行実験のほか、交通安全環境研究所とともに都営バスによる実証実験を行っている。
資源枯渇や環境問題などから、エネルギー業界全体の転換期などといわれており、石油業界の研究開発部門の役割が問われているのではないだろうか。昭和シェル石油の研究所は、既存製品の時代のニーズにマッチした性能向上と、新規ビジネスにつながる基礎研究に取り組んでいるそうだ。