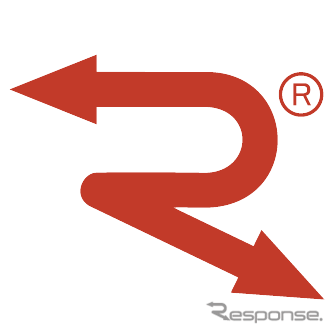ブレーキチューンの花形といえばキャリパー交換だ。見た目にもキャリパー本体を交換することで、そのドレスアップ効果は高い。そして、もちろんその効果も高いが、キャリパー交換は制動距離が短くなるわけではない。でも、大きな効果を持つチューニングパーツなのだ。
◆キャリパー交換の魅力とブレーキの仕組み
ブレーキはペダルを踏んでマスターシリンダーを押し、フルードを押し出す。そのフルードが配管を通ってキャリパーに伝わり、キャリパー内部のピストンを押し出し、その先にあるパッドがローターに押し付けられて摩擦を起こして減速している。
このキャリパーは、純正品の多くが片押しと呼ばれるタイプだ。片側にあるピストンがパッドを押し、反対側のパッドはその反作用によってローターに押し付けられている。スポーツモデルや重量のある高級車になると、ローターの内側にも外側にもピストンが配置される対向キャリパーが採用されることが多い。両側にピストンがあることで均一にパッドを押し付けることができるのがメリットだ。
そして、高性能なキャリパーはこのピストンの数が増えていく傾向にある。純正では片押し1ピストン(potと呼ばれる)だったが、アフターパーツメーカーのキャリパーだと内側と外側に2個ずつ、合計4つのピストンがある4potや、内側と外側に3個ずつ、合計6つのピストンがある6potも使われることが多い。
◆ピストン数と制動力の関係
ピストン数を増やせば効くようになるわけではない。基本的に純正2potでも対向6potでも、ピストンの面積は同じである。ペダル側のマスターシリンダーが同じものなら押し出される量は一定なので、ピストン数が増えても同じ面積にしなければきちんと作動してくれないのだ。
ピストン数が増えて面積も増えてしまうと、ブレーキペダルを強く踏まないとブレーキの効きが弱くなる。あえて踏みごたえのあるブレーキペダルにするために、そういった設計のキャリパーを使うレースなどもあるが、ストリートではとっさのときに効きが弱いこともあり危険なのだ。ブレーキメーカー側では、もちろんそういったことを考慮して設計し、車種適合を確認している。そのためサイズ的には装着できても使えない車種なども存在するのだ。
そしてピストンの数が増えていくことのメリットは、パッドを均一に押せること。均一に押せるからこそ、パッドとローターが均一に摩擦してくれる。より制動力も引き出しやすくなるのだ。しかし、いかんせんどんなにブレーキが効いてもタイヤのグリップを超えてしまっては意味がない。
ここ数十年のクルマでブレーキを思い切り踏んでタイヤがロックするか、ABSが介入しないほどの制動力しかないクルマはまずない。トラックなどは別だが、乗用車であれば強く踏めば驚くほど効くはず。しかし、そこでタイヤがグリップを失っては意味がない。そのギリギリの領域をいかに使えるかがカギになる。
◆キャリパー選びと注意点
サーキット走行ではABSが介入するかどうかの絶妙なところでブレーキングしたり、そこからリリースをして、タイヤのグリップに余裕をもたせながらハンドルを切っていく必要がある。その絶妙なコントロールがしやすいため、キャリパー交換の意味があるのだ。
タイヤの性能を引き出しやすくなるからこそキャリパー交換の意味がある。つければ短く止まれるわけではないのだ。単純に短い距離で止まるだけなら、グリップの高いタイヤを履くことが最も近道でもある。この絶妙なコントロール性を持たせるためにキャリパーは高い剛性を持ちつつも、絶妙にしなることでそのコントロール性を生み出している。そこには高いノウハウが必要となっている。
素材も鍛造アルミの1ピースモデル、鍛造アルミの2ピースモデル、鋳造アルミの1ピースモデル、鋳鉄製などがある。それぞれ特性があるが、一般的には鍛造1ピースが最も軽く作れるため、バネ下重量を抑えて運動性能を向上させる効果的な選択となる。鋳鉄製はトラックやトヨタ『ハイエース』などの重い車用にラインアップされている。
さまざまなメーカーのキャリパーがあるが、その後のオーバーホール時に必要なパーツの供給や、そもそもの信頼性の高さとなると、有名メーカーのキャリパーをオススメしたい。海外製の安価なキャリパーにはコピー品のようなものもあるので、気をつけていただきたい。