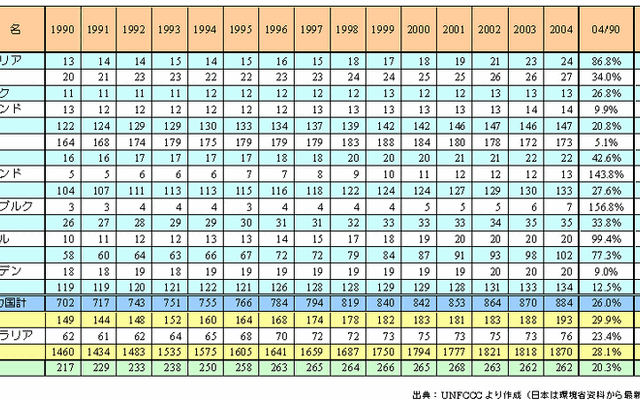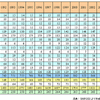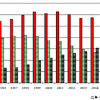各国の運輸部門CO2はどうなっているか
自動車や電化製品からのCO2排出総量は、なかなか減らないのが実情だ。1台1台の省エネ性能は上がっていても、保有台数や活動量の増加がそれを上回ってしまう。例えば自動車の燃費が平均10%アップしても、保有台数や総走行距離が20%増えると、CO2は10%増えてしまう。
2001年度をピークに運輸部門のCO2が減少傾向となったのは、保有台数や走行距離の伸びが頭打ちになったことが一因にある。日本以外の国でも同じようにCO2は減っているのだろうか。残念ながら、ほとんどの国で運輸部門のCO2は増加を続けている。
◆主要国はすべて90年比で増加
温暖化対策の国連事務局(UNFCCC)は、主要国の運輸部門CO2の統計を公表している。表1は、うちEU15か国、カナダ、オーストラリア、アメリカと日本のデータを示したものだ。
1990年と04年の比較では、すべての国が増加だ。EU15か国では合計26%増で、日本の20%より増加率は大きい。1か国で排出量が1億トン超となるEU主要4か国のうち、ドイツとイギリスの増加率は10%前後と小さいが、フランスは日本とほぼ同じ21%、イタリアは28%の増加だ。
またオーストリア、スペイン、ポルトガルといった国々では、排出量は少ないものの伸び率は倍近い。アメリカは、排出量が04年で18億7000万トンと突出しており、90年比の増加率もカナダとともに30%近い。
◆減少に転じたドイツと日本
2000年と04年の比較で減少に転じているのはドイツと日本だけだ。生真面目な両国の国民性が反映されているような気がして面白い。ドイツは99年をピークに減少に転じており、90年比の増加率も小さい。日本は、01年をピークにわずかながら減少している。なお表にはないが、日本は05、06年も引き続き減少している。
ドイツに限らず、ヨーロッパでは主にディーゼル乗用車への転換によって燃費を改善してきている。ディーゼルはガソリンより20%程度燃費が良く、走行距離あたりのCO2も少ない。欧州メーカーのヨーロッパでの新車販売台数は、04年にはディーゼル乗用車がガソリン車を上回る水準となっている(図1)。
日本では、排ガス規制のクリアが難しいことなどからガソリン車が中心だ。排ガスのクリーン化やコスト面の目途が立てば、ディーゼル乗用車は日本でもCO2削減の有力な手段になるだろう。