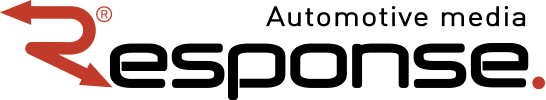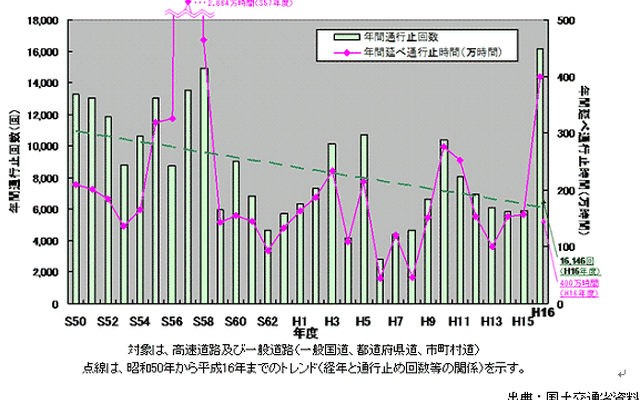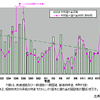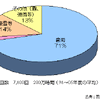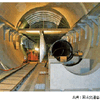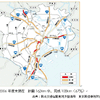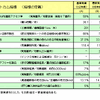道路の防災対策
道路行政では5年ほど前から、事故や災害、環境負荷軽減などアウトカム(成果)目標を指標化し、その達成度を評価している。今回は、災害の予防や復旧に果たす道路の役割や評価について考えてみたい。
道路の防災対策というと、土砂崩れを防ぐのり面の補強、橋や高架などの耐震性強化を思い浮かべる方が多いと思う。自然災害による道路の通行止めは、長期的には減少傾向にあるものの、過去10年間で年平均7800回起きており、その7割は豪雨によるものだ(図1、2)。
1996年に行われた道路防災総点検では、要対策箇所が全国で10万4000か所あったそうだ。そのうち対策が完了したのは05年末段階で35%に過ぎず、依然として6万8千箇所が未対策なままだという。
◆道路の防災機能
その他にも道路が持っている防災機能がある。道路幅を広くとれば延焼防止になり、地震で建物や電柱が倒壊しても避難や救援などに支障が出にくい。阪神・淡路大震災の経験では、道路幅が12〜15mあると延焼や避難・救援に支障が出ないとされている。
また、リダンダンシー(Redundancy、冗長性)と呼ばれる被災箇所の迂回路確保も重要な機能だ。04年の新潟中越地震では、不通になった国道17号や関越道に代わり上信越道や磐越道が役立った。集中豪雨で不通となった国道の代替路として高速道路が無料化された例もある。
◆ライフラインの保全と地下共同溝
近年、集中豪雨や地震など大規模な災害が頻発している。首都直下地震では死者1万人、100兆円規模の被害が想定されるなど、大都市圏で大地震が発生すると被害は桁違いだ。
都市の幹線道路の地下には、電力、ガス、通信、上下水道などライフラインを集約する共同溝(きょうどうこう)というトンネルが掘られている(写真)。幹線部分では直径8mにもなる大規模なものだ。共同溝は都市防災の核となるインフラだと思うが、これも整備途上にある(図3)。
表1に示す道路行政のアウトカム指標のうち、防災対策は「(4)広域救難ルートの確保」、「(5)「防災上課題のある市街地の割合」の2つが挙げられているが、少し不足しているように思う。山間地での通行止め、リダンダンシー、ライフライン保全など、耐性や信頼性を多様に評価する指標が必要だろう。