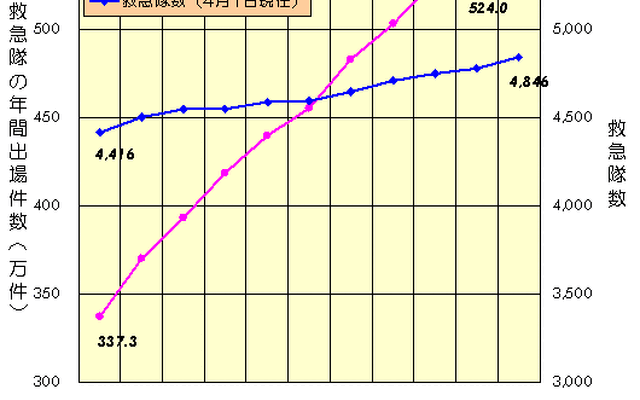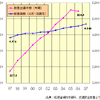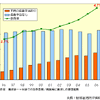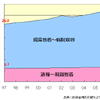救急ニーズの急増と救命率
昨年来、医療機関の救急搬送受け入れについての報道が相次ぐなど、救急医療が注目を集めている。救急医療にとって、医療機関とともに救急搬送の果たす役割は大きい。今回は、交通とも深い関係のある救急搬送について考えてみたい。
救急医療が問題となった背景には救急の需給逼迫がある。患者の急増で救急隊の出場は10年間で1.5倍、年520万回を超えているのに対し、救急隊は1割ほどしか増えていない(図1)。出場の内訳は急病が60%、一般負傷13%、交通事故12%となっており、今後交通事故は減るとしても、年500万回の水準がしばらく続くだろう。
重篤患者の救命は一刻を争う。救急救命士の養成、市民向け応急手当の講習、ドクターカー・ヘリ配備など現場の応急治療を重視した対策が効を奏し、家族など市民が応急手当するケースは増え、救命率は着実に上昇している(図2)。
◆遅延傾向にある搬送時間
しかし、救急車の搬送時間は遅延傾向にある。通報後、救急隊が現場に到着するまで6.6分、病院に収容するまでは32分かかっており、97年から06年でそれぞれ0.5分、6分遅れている(図3)。さらに、この統計には表れない事故の発生から通報まで約10分のタイムロスも無視できない。通報者が動転していたり現場の地理に不案内であるためだ。
遅れの原因は、医療機関、救急隊の双方とも繁忙状態にあること、また地方では医療施設が減りつつあることが大きい。また携帯電話からの通報が増加したことで事故現場の特定に時間がかかることも一因と言われる。
◆目標を掲げることが重要
救命救急の目的は、救命率を上げ負傷者の予後を良好にすることだ。そのためには、まず目標を掲げることが大事だ。交通安全では首相談話“10年間で交通事故死者数を半減する”が推進の大きなトリガーになった。「重篤患者の救命率を○%に向上」、「救急搬送時間を○分短縮」など目標を掲げることが、関係者の連携を促し対策を実効あるものにする。
搬送時間を短縮する上で有効な交通対策は何だろうか。GPS携帯やカーナビから発生地点が自動的に伝わる緊急通報、青信号の連動による緊急車両の優先通行、高速道路上の出入り口を増やす、サービスエリアをヘリポートとして活用するなど、ITSや道路の整備改良は搬送時間の短縮に貢献するはずだ。
また、救急隊や医療施設の大幅増が望めないとするなら、真に救急を必要とする患者を優先することも考えざるを得ない。横浜市は昨年、119番の段階で救急搬送の必要性を判断する「コールトリアージ」の導入を決めた。今後の動向には注目したい。