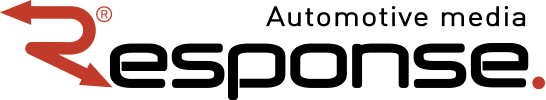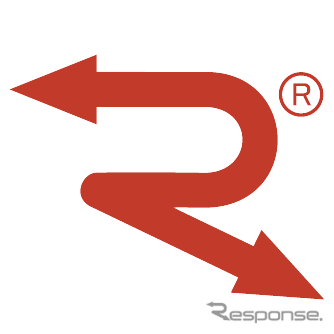GMとSAICが新世代エンジンを共同開発
空前のクルマブームを追い風に、目下、世界最大の自動車市場となっている中国の自動車業界から、また大きなニュースが飛び込んできた。米ゼネラル・モーターズ(GM)は中国における合弁相手である上海汽車工業集団(SAIC)と、エネルギー効率を大幅に高めた新世代エンジンの共同開発を行うと発表したのだ。
新世代エンジンは1〜1.5リットル級の直噴ターボエンジン。燃焼状態を精密にコントロールすることで、ターボでありながら自然吸気エンジンと同様に熱効率の高い理論空燃比で運転可能とし、ターボでトルクが増強されるぶん排気量を減らしてエンジンの内部摩擦抵抗を削減する、いわゆる“ダウンサイジングエンジン”と呼ばれるユニット。今日の自動車用量産エンジンとしては、最新技術の部類に属するものになると思われる。それでいて、搭載する車種は利幅の大きい高級車ではなく、廉価な大衆車であることが排気量から類推される。
GMはこの先進的なエンジンを一方的に技術供与するという形ではなく、デトロイトのGM開発拠点と、上海にGMとSAICが合弁で設立したパン・アジア・テクニカル・オートモーティブ・センターの二極で、文字通り共同開発するという。
◆一線を踏み越えたGM、他メーカーへ影響
中国の自動車ビジネスの中でも異例の決断と言える。これまでも、中国資本との合弁会社の開発機能を強化する動きは活発化していた。ホンダは今年4月の北京モーターショーで、広州汽車集団(GAC)との合弁会社、広州本田の独自ブランドモデル「理念」のコンセプトモデル第3弾を展示し、時機をみて量産を開始することを示唆した。他メーカーも中国のユーザーの好みに合わせたデザインの中国専用モデルを合弁会社で盛んに作るようになった。
が、それらのモデルのほとんどは一世代、あるいはさらに過去のプラットフォームを使ったものだ。先端的ではなくなった技術で良いものについては積極的に移転し、一方で次世代エンジンやハイブリッドパワートレイン、EVなどの将来技術については競争力の源として、ノウハウを先進国メーカー側が囲い込んで優位性を維持するというのが、一般的なビジネスモデルだったのだ。
今日、中国はCO2排出規制を大幅に強化することにしており、新たなCO2規制に対応するにはエンジン性能を向上させる必要があるというのは事実だ。が、その規制対応よりハイレベルな最新の環境性能を持つエンジンを中国側と共同開発するというGMの判断は、これまでのビジネスモデルが守ってきた一線を明らかに踏み越えている。
日本メーカーをはじめ、中国で合弁生産を行っている外資メーカーは、このGMの決断の影響を受けずにはいられないだろう。GMはただでさえ、中国版“ビッグスリー”のポジションにある有力メーカーだ。そのGMのクルマの商品力が飛躍的に上がれば、他メーカーもそれに追随せざるを得なくなる。中国トップブランドのフォルクスワーゲンをはじめ、各社がこれまで展開してきた“高い技術は高い価格で”という戦略は取りづらくなるだろう。
◆ライバルになりかねない共同開発相手
一方、GMにとっても将来的には商売敵になるかもしれない中国の合弁企業と先進技術を共同開発することは、それなりのリスクを伴なう。SAICは独自ブランドのクルマの開発も行なっており、将来的にはオリジナル車の輸出を目指している。
そのSAICの技術力は、GMとの共同開発によって確実にボトムアップする。GMとの協業で技術力を大いに高めた例は過去にもある。日本のスズキもその一社で、鈴木修会長兼社長は「GMはクルマ作りの先生だった。きちんとしたクルマ作りができるようになったのもGMのおかげ」と振り返る。しかし、SAICはスズキやサーブとは比較にならない巨大資本で、合弁系では生産台数首位メーカー。10年スパンでみれば、グローバル市場でもGMとライバル関係になる可能性は十分にあるのだ。
自動車メーカーの元開発系幹部で、今は別業界に転じたOBの一人は、なぜGMがこのような決断を下したのかということについて概ね3つのファクターが考えられると語る。その中身は次のようなものだ。
(1)巨大化した中国市場が今後も急成長すると見込み、競争力強化とシェア獲得のためになりふり構わず先進技術を放出。
(2)長年のグローバルビジネスの経験から、合弁相手から技術のライセンス料をきっちり取り、継続的に収益を上げられる自信がある。
(3)内燃機関についても技術のコモディティ化(普遍化・汎用化)が進むと見込んでおり、技術の囲い込みより開発スピードアップやコスト削減を重視することにした。
◆囲い込みより重視されたこと
このうち、特に気になるのは3番目だという。シミュレーション技術やCAE(コンピュータ支援設計)の進化で、エンジン開発は昔に比べてメーカー間の格差がどんどん埋まっている。とりわけ新興国メーカーの技術力向上のスピードは、想像以上に速い。シミュレーションもノウハウの積み重ねであるため、完全に肩を並べるようになるわけではないが、エンジン技術を囲い込んでいれば決定的な商品力差を保てるというような時代ではなくなっているのも事実なのだ。
「GMは極めて高いエンジン技術を持っていますが、もしそう考えてエンジン技術を設計プロセスまで含めて合弁相手に明かす決断をしたとしたら、ずいぶん思い切ったものだと思います。もちろん英断かどうかは今後を見なければなりませんが」
すでに高所得層向けには、旧式技術のクルマが売れるほど甘くはなくなった中国の自動車マーケット。低所得者層向けに30年前の基本設計のクルマが格安で売られるといったシーンはこれからも当分なくならないだろうが、合弁会社が作る大衆車モデルの新車を買うような中産階級ユーザーに向けても、新技術を積極的に投入しなければならない段階に入りつつあるのか。