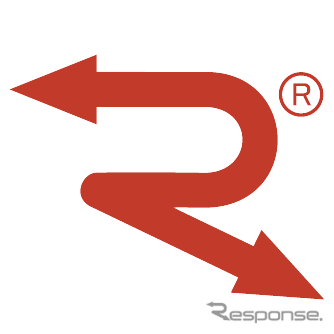ホンダの主力サブコンパクトカー『フィット』が昨年、マイナーチェンジを受けた。先進安全システム「ホンダセンシング」設定、ボディ補強、ハイブリッドシステム改良など変更幅は大きく、短距離試乗の印象はきわめて良かった。が、クルマというものはチョイ乗りではわからないもの。その改良版「フィットハイブリッド」で800kmほどツーリングし、色々な道路で改良版フィットの特性を観察してみたのでリポートする。
試乗車はフィットの最上位グレードである「ハイブリッドS」。合成出力137psを発生するハイブリッドパワートレインを搭載。静粛性を高める防音ガラスをウインドスクリーンおよび前ドアの窓に使用。パドルシフト付きステアリング、スポーティタイヤ、エアロバンパー等々、充実した装備とデコレーションを持つ。ただしサスペンションセッティングは他のハイブリッドグレードと同じ。
ドライブルートは東京を出発し、まずは御殿場から甲斐の山々を越えて甲府へ。その後、長野県は北アルプスの安房峠、および中房温泉へ。帰路は長野の岡谷、霧ヶ峰ビーナスラインの和田峠、国道254号線内山峠などを経由して東京へ向かった。道路のおおまかな比率は市街路2、郊外路4、山岳路3、高速道路1。路面コンディションは全区間ドライ。1~2名乗車。エアコンAUTO。
2年前のゴールデンウィーク期間のことだが、筆者は改良前のフィット「ハイブリッドLパッケージ(改良後のハイブリッドL)」で3700kmあまりツーリングしたことがある。それと比較しつつ新フィットのトータルな印象を箇条書きにしてみた。
■ポジティブ
1. 乗り心地、静粛性が劇的に向上した
2. クルマの動きがしなやかになった
3. ハイブリッドシステムのギクシャクが消えた
4. 渋滞追従機能はないが先進安全システムがついた
5. サブコンパクトとしては相変わらず圧倒的な室内ユーティリティ
■ネガティブ
1. ツボにはまった時のDCTハイブリッドの驚異的な切れ味が消えた
2. Lとのタイヤの差を勘案してもなお実効燃費が少なからず下がった
3. いささか退屈なドライブフィール
4. 新型のLEDヘッドランプの照射範囲が狭く、夜間走行は不安
5. 全長が4mを超え、フェリー料金が上がった(今回は実害なし)
では、実際のツーリングに照らし合わせながら、インプレッションを進めてみよう。
◆フルモデルチェンジ並みにシャシー性能が激変
まずは激変したシャシー性能から。これは改良前に対し、最もアドバンテージの大きなファクターと言える。改良チームのエンジニアによれば、ボディを補強し、車体への入力の受け止めを変えたとのことだったが、それによる進化幅はフルモデルチェンジ級に近いものがあった。
サスペンションのストロークやボディ重量を受け止めるアッパーマウントラバーの変形が素直になった。直線道路でアンジュレーション(路面のうねり)や荒れた舗装部分を乗り越えても前期型のようにガタガタという振動にならず、ゆるゆるといなした。乗り心地やドライブフィールの質感は大幅に向上し、また直進感も良くなった。
山岳路でハンドルを切ったときのフロントサスペンションの沈み込みもスムーズで、前が突っ張ってアンダーステアが出やすいという悪癖は消えた。対角線ロールの姿勢変化がつかみやすく、あれこれ考えなくてもドライビングを組み立てられるのは、ロングランナーとしてみてもなかなかの得点の高さ。また、クルマの動きがわかりやすいことは同乗者にとっても山岳路ドライブのストレスを緩和する効果があるようであった。
ただ、安曇野から燕岳登山道付近の中房温泉に向かう山岳路やビーナスラインと交差する和田峠といった、本格的に悪い道になると、この美点は薄れてくる。コーナーの途中で深いアンジュレーションやギャップを拾ったりすると、ダンピングのやや弱いショックアブゾーバーがボディの上下方向の揺動を止められなくなり、グリップ抜けが発生しやすくなる。もっとも、これは秘境ドライブもやってみたいというカスタマーを想定したハイレベル領域の話であって、実用上は問題はない。
もう一点、クルマの動きはつかみやすいがステアリングインフォメーションは案外希薄で、ちょっとぐにゃついたフィールがついてまわる。ロングドライブ時にはちょっと退屈に感じられるかもしれない。これもクルマの快適性、安心感の生む高揚感である程度相殺されるので大きな問題ではないが、路面追従性や乗り心地の改善とシャキッとしたドライブフィールの両立は全面改良まで待つ必要があろう。
◆DCTハイブリッドの完成形に近づいた
次にパワートレイン。まず、デビュー後5回ものリコールを出してしまったいわくつきのDCT(デュアルクラッチ自動変速機)ハイブリッドだが、今回の改良で変な動きはほぼ完全に封じ込められたと言っていい。普通に運転しているかぎりは、市街地、高速、山岳路とも終始、動きは滑らかだった。苦手だった低速域でのEV走行からハイブリッド走行への移行もスムーズ。
スロットルをわざとパカパカ開け閉めしたりすると若干のスナッチ(前後方向のガクガク)が発生することもあるが、MTや直結型ATでは普通にあるレベルで、気にするほどのものではなかった。少なくともスムーズネスについては、先に出たミニバン『フリード』に続き、ようやくDCTハイブリッドの完成形に近づいたと言ってよさそうだった。
スムーズネスと引き換えに失ったものもある。それは前期型が持っていたレーシングDCTを思わせるような変速の切れ味だ。試乗車にはパドルシフトが装備されていたが、変速時に次の段と回転をぴたりと合わせてスパッと変速するのではなく、半クラッチを多用するヌルッとしたフィールになり、シフトチェンジの楽しさは失われた。
また、フリードでも感じられたことなのだが、ギア比が変更されたことで加速時に2速、3速、4速…と、同じ回転域を使いながら気持ちよく変速する感覚も薄れた。山岳路では3速と4速がやや離れすぎており、ギアの選択でやきもきさせられるシーンもあった。別にこれで実用的な問題があるわけではないし、合成出力137psというパワーも十分に素晴らしいのだが、元々がフィットGTIとでも呼びたくなるような爽快な伸びきり感を持つパワートレインだっただけに惜しく感じられた。
もう1点、ちょっと気になったのは燃費。前期型は「これだけハイペースで走ってもこんなに燃費がいいのか!!」とちょっと嬉しくなるような燃費を記録していたのだが、改良型で同等の燃費を出すにはスロットルワークにかなり気を使う必要がありそうだった。
燃費を計測した区間は合計735.1kmで、給油量は合計36.44リットル。満タン法計測での燃費リザルトは20.2km/リットルだった。東京を出てから甲斐、飛騨などの山地を中心にドライブし、長野の塩尻までスパルタ気味に走った485.4km区間が18.9km/リットル。そこからややエコラン気味に東京まで走った249.7km区間が23.2km/リットル。
サブコンパクトとはいえこれだけ大きな室内容積のあるクルマがリッター20kmも走れば十分と考えることもできるが、改良前ハイブリッドLパッケージに比べると2割前後のビハインド。また、フィットハイブリッドより車両重量が200kg以上重く、ファイナルギアも低い『フリードハイブリッド』のロングラン燃費と大してかわらないというのはいただけない。原因は不明だが、リチウムイオン電池が満充電となってもモーターのみの走行になかなか切り替わらないといった挙動があったので、何らかの保護作用が働いていたのかもしれない。
◆ユーティリティの高さが光る
現行フィットは登場したての頃からユーティリティの高さではBセグメントサブコンパクトのライバルと比較してもお手本と言える存在だった。それは大規模改良を経た今でも変わっていない。
リアシートの足元空間の広さだけならスズキ『バレーノ』、日産『ノート』など他にも優れたクルマはあるが、室内空間と荷室のバランスが取れ、またリアシートの座面高さが適切で開放感のある眺めを得られるといった、パセンジャーカーとしての質の高さは随一と思われた。2人でのお出かけなら趣味のための道具を大量に積み込んでの長旅も受け入れるだけの余裕があり、旅館泊なら4人+荷物もまったくの余裕である。
フィットの上にはステーションワゴンの『シャトル』もあるが、荷室容量によほどのこだわりでもない限り、それを必要としないくらいのユーティリティだ。今回の改良で乗り心地や静粛性が大幅に向上したこともあって、フィットを駆ってのたまの遠出もより楽しいものになるだろうと思われた。
その遠出をより安全・安心なものにするのに有用な先進安全システム「ホンダセンシング」は、機能、性能ともトップランナーというわけではないが、有用性は十分だった。ステアリング介入型の車線維持アシストもあるし、前車追従クルーズコントロールもある。手放しに近い運転を許容するわけではないが、同じシステムを実装するフリードハイブリッドと同様、疲労軽減効果は少なくなさそうだった。
不満があるとすれば、30km/h以下の追従に対応しておらず、微低速になるとキャンセルされてしまうことだが、筆者はシステムに頼った運転が好きではなく、システムオンでも基本的には自力でドライブしていたため、それがヒヤリハットにつながることはなかった。ないよりはあったほうが絶対にいいことは確かである。
改良版フィットの安全面で先進システムよりむしろ気になったウィークポイントはヘッドランプ。試乗車には新デザインのLEDヘッドランプが標準装備されていたが、その照射範囲が狭いのだ。具体的にどういう感じかというと、目の前にカーブが現れると、真正面のガードレールは明るく照らし出されるが、コーナーの奥に目線を向けるとそこに照射範囲の境界線がくっきりと出て、その先はほとんど光が届かず真っ暗。ロードランプを使っても解消されなかった。
夜間の山岳路でも松本から上高地・乗鞍に向かう国道158号線のように随所に照明灯が設置されているところはまだいい。が、照明のほとんどないワインディングロードでは低速で走ってもなお先を見通せず、走ること自体が恐く感じられた。
遠乗りにも使えるギアとしての価値を持たせるなら、照射範囲を広げるか、せめてコーナリングランプを設けてほしいところ。また、今や軽自動車でも珍しくなくなりつつあるハイ/ロー切り替えのみのシンプルなアクティブハイビームすら持たないというのもネガティブに感じられた。
◆マルチなバランスで群を抜く
フィットはもともとこれ1台で日常ユースから遠出までをこなせるマルチパーパス性、長いサスペンションストロークを持たせた優れた基本設計等々、サブコンパクトクラスとしては実力派だった。昨年の大型改良で弱点であった安っぽいフィールが解消され、競争力は非常に強いものになったと言っていい。
前述のようにライティングに関する考え方が後進的なので夜に暗い道を走る機会が多い人には勧められないが、昼間の移動が中心であるならば、下駄がわりのクルマでレジャーにも旅行にも行くといったアクティブライフ好きの顧客にとって購入リストのトップ3に常時入れておいていいクルマと言えそうだった。
ライバルは国産サブコンパクトモデル全般だが、普通のハッチバックモデルでありながら前後席および荷室がバランスよく広いというユーティリティの高さ、走り、快適性、経済性のウェルバランスぶりでフィットを上回るモデルはそう多くない。あとは、クルマに何を求めるかによってチョイスが分かれるところであろう。