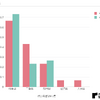レイ・フロンティアが、大型連休中、特定警戒都道府県についてそれぞれの越境移動の状況を可視化するため定点観測データを適宜公表していくと発表した。
同社公式ブログによれば、現在特定警戒都道府県に指定されている、北海道、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の13エリアについて、4月27日から5月10日までの期間、それぞれの都道府県から、越境となる流出移動を計測する。
更新状況は同社の公式ツイッターアカウントにて発信される。大きな動きがあればリリース等の対応、さらに大型連休終了後にサマリーの発表もされるという。
緊急事態宣言は4日も正式に延長が発表される予定だが、現在問題になっているのは、都道府県ごとの要請や制限の解除は、越境移動、つまり感染者の多いエリアから少ないエリアへの移動、少ないエリアから多いエリアへの移動が増える可能性があることだ。とくに関東エリア、中京エリア、京阪エリア、福岡エリアなど、隣接都府県と経済圏を構成している地域では、圏内移動の抑制が鍵となる。
すでに発表されたグラフでは、東京は、神奈川、千葉、埼玉との相互の移動が多いことが見て取れる。ベッドタウンとしての通勤と商業圏の物流のつながりが可視化されている。同様に名古屋は岐阜・静岡とのつながりが確認できる。大阪は、兵庫、京都の3都市に近畿エリアが加わっている。
 4月27日と28日の移動の変化も現れている。28日は平日だが翌29日が大型連休初日にあたるため、すでに通勤や物流の移動が減少している。しかし、注目したいのは、石川県の神奈川県への移動が28日だけ増えているように見える(27日はほぼゼロ)。同様に愛知県では、三重県への移動が27日に比べて28日が増えている。大阪府であれば京都府への移動が同様な動きになっている。
4月27日と28日の移動の変化も現れている。28日は平日だが翌29日が大型連休初日にあたるため、すでに通勤や物流の移動が減少している。しかし、注目したいのは、石川県の神奈川県への移動が28日だけ増えているように見える(27日はほぼゼロ)。同様に愛知県では、三重県への移動が27日に比べて28日が増えている。大阪府であれば京都府への移動が同様な動きになっている。

 グラフのデータには、物流や医療関係者など自粛対象ではない移動も含まれているので、断定はできないが、大型連休前日のレジャー・帰省の移動によって増えている可能性がある。緊急事態宣言に伴う外出自粛要請は大型連休中も有効である。本格的な連休が始まる5月2日の動きにも注目したい。
グラフのデータには、物流や医療関係者など自粛対象ではない移動も含まれているので、断定はできないが、大型連休前日のレジャー・帰省の移動によって増えている可能性がある。緊急事態宣言に伴う外出自粛要請は大型連休中も有効である。本格的な連休が始まる5月2日の動きにも注目したい。