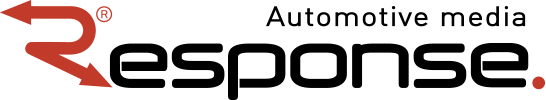鈴鹿8耐で8位に入ったシングルレーサー「ロードボンバー」
キャンディーズが解散し、江川卓が空白の一日を経て巨人入りし、沖縄の道路が左側通行になった年。それが1978年のことである。
鈴鹿8時間耐久ロードレースが初開催されたのも同年7月のことで、スズキ『GS1000』を送り込んだヨシムラがホンダワークスの『RCB1000』を退けて優勝。記念すべき第一回大会の覇者になった。
リザルト上位にはヤマハ『TZ750』やカワサキ『Z1』といった大排気量・高出力の重量車が名を連ねていたわけが、ひときわ小振りなマシンが8位でチェッカーを受けている。それがロードボンバーと呼ばれたシングルレーサーだった。
これ以上ないほどスリムな車体に498ccの空冷単気筒を搭載し、燃費のよさと機動性の高さを活かして快走。ピットインの回数を減らし、8時間の長丁場をタイヤ無交換で走り切るという奇襲作戦で大きな戦果をあげたのだ。
ベースになったエンジンは、1976年にヤマハから発売されたオフロードバイク『XT500』のものだ。このモデルは欧米でヒットを記録。パリ・ダカールラリー(1979年)ではワン・ツーフィニッシュを果たし、一躍その名を知らしめた。
 1976年当時の販売店向け冊子「ヤマハニュース」の表紙を飾った「XT500」
1976年当時の販売店向け冊子「ヤマハニュース」の表紙を飾った「XT500」
ロードボンバー誕生のきっかけは、雑誌の企画だ。XT500に可能性を見出した『モト・ライダー』誌の鈴木脩巳編集長が、島英彦氏に設計を打診して制作。そのカフェレーサースタイルが、BSAやノートンのスポーツシングルに憧れる潜在的なユーザーの物欲を刺激して大きな話題を呼んだ。当初の目論見はナンバーの取得だったものの、法規制の壁をクリアできず、これは断念せざるを得なかった。
とはいえ、そのままお蔵入りさせるのはあまりにも惜しく、レース参戦へとプロジェクトの方向が変わった。1977年、まずは鈴鹿8耐の前身になった6時間耐久レースにエントリーし、18位で完走。国際格式レースとなった翌78年の活躍は既述の通りだ。
さて、ここまでは前振りである。『SR』の出自を語る上で、このXT500とロードボンバーの存在を無視するわけにはいかず、豆知識のひとつとして覚えていてもらっても損はないと思う。
新しい価値観をマーケットに吹き込んだ初代SRの登場
 北米向けの初代「SR500」
北米向けの初代「SR500」
初代ヤマハSRの発売は、1978年3月のことである。時系列的には、オフロードで躍動したXT500と鈴鹿8耐で快走したロードボンバーの間を繋ぐ存在と言ってもよく、やはりXT500のエンジンを流用したベーシックなモデルとして送り出された。ロードボンバーにヤマハはまったく関与していないのだが、その活躍とSRの発売タイミングが上手くマッチ。単気筒の可能性を知らしめる、新しい価値観をマーケットに吹き込んだのである。
XT500をロードスポーツに仕立て直すという発想は、欧米では自然のなりゆきだった。カスタムやチューニングを楽しめる素材として、シンプルな単気筒は恰好の素材であり、趣味性を大切にする層に受け入れられたのである。
大半の国にはXT500と同じボア×ストロークを持つ「SR500」が投入されたが、規制の関係で欧州の一部には、ストロークを短くした「SR400」も用意。日本では、そのどちらも選ぶことができた。当時の価格は、SR500が35万円、400が31万円というもので、日本における500と400のダブルラインアップは1999年モデルまで続いた後、400が残った。SR500製造中止の背景は、需要の低下や排ガス規制の影響である。
需要の低下と排ガス規制。結局のところ、SRの歴史はこのふたつの要件への抗いだ。1978年の誕生から2021年の今に至るまで、その繰り返しだったと言ってもいい。
時代に左右されることなく作り続けられてきた不変性が語られるが、ただ単に生産ラインを止めなかったわけではない。無理難題な規制をクリアするくらいなら新型に刷新してしまった方が合理的だった時でさえ、開発陣は創意工夫を凝らし、ショップとユーザーはセールスでそれを支えた。その結果が、43年という超ロングセラーにつながったのだ。
同士討ちを回避し、少しずつ改良を重ねた80年代から2000年代初頭
 ヤマハ SRX600(1985年)
ヤマハ SRX600(1985年)
最初の大きな危機は、他でもないヤマハの同士討ちだった。というのも、1985年にSRの進化版とも呼べる『SRX400/600』が登場。ヤマハはそれを、SRの後継モデルと明言していた。軽く前傾して搭載されたエンジンとセパレートハンドル、そしてショートマフラーの組み合わせはいかにもスポーティで、ヤマハの想定を上回るセールスを記録したのも当然だろう。
一方のSRは、ディスクブレーキをドラムに変更するなど、よりクラシカルな方向に舵を切りながらも、販売台数は徐々に下降。90年代を迎えることはないと思われた。
ところが、SR存続の気運がヤマハ社内で少なくなかったこと、レーサーレプリカブームに陰りが見え、クラシックが再評価されつつあったこと、SRのカスタムを手掛けるショップとそれを支持するユーザーの熱量が思いほか強かったことなど、様々な要因が重なって生産の継続が決定した。
キャブレターとカムシャフトの変更(1988年)、アルミパーツのバフ仕上げや塗装変更による質感の向上(1991年)、点火ユニットの改良や安全装備の充実(1993年)、ライディングポジションの最適化(1996年)、フロントディスクブレーキの復活とキャブレター変更(2001年)、スロットルポジションセンサーの採用(2003年)といった具合に、80年代後半から2000年代初頭にかけて、大小様々な改良が盛り込まれ、安定した人気を博したのだ。
2003年には誕生25周年を記念したオーナーズイベントが全国各地で開催され、順風満帆といったところだったが、ほどなく、再び存続の危機にさらされるようになった。それが新しい排ガス規制の施行である。
執念の改良でクリアした排ガス規制
当時、この規制を前にすでに2ストロークモデルは絶滅。250ccの4ストローク4気筒も軒並みカタログ落ちし、ヤマハのみならず国産メーカーのラインナップは激減していった。
空冷単気筒も例外ではなく、さすがにSRもここまでか……と思いきや、ヤマハはキャブレターをインジェクションに換装して2010年モデルとして発表。これによって始動性も向上することになり、新たなユーザー層を開拓することになった。
ここまでくると、ほとんど執念である。インジェクション化の後は、カスタムブーム、ネオクラシックブームの波に乗って欧州でも再販されたほど、大きなアイコンへと成長したのだ。
 ヤマハ SR400。写真は2018年に復活した際のモデル。
ヤマハ SR400。写真は2018年に復活した際のモデル。
ところがそれも束の間。さらに厳格化された排ガス規制の施行が決まり、2017年についに生産終了のアナウンスがなされた。それ以前はあくまでも噂が先行し、その度にヤマハは先手を打つカタチで延命してきたわけだが、この時はSRに次ぐヤマハのロングセラー、『セロー』も同時に生産を終え、長年のファンは悲しみくれた……わけでもなかった。
なぜなら、規制への対策を施し、近い将来復活させることを事前に予告。これ自体、非常に稀なケースなのだが、実際に約1年のインターバルを経て、2019年モデルとして再デビューを果たしたのだ。外観の変更は最小限に留められ、エンジン前部に蒸発ガスの大気放出を防ぐキャニスターの追加程度で済まされた。
2021年10月からのABS義務化、そして「SR400ファイナルエディション」
 ヤマハSR400
ヤマハSR400
しかしながら、このイタチごっこがいつまでも続くとは限らず、いよいよ末期かもしれない。SRと同じように歩んできたセローはすでに継続を断念し、「セロー250ファイナルエディション」の名で、2020年モデルをリリース。車名の通り、これが本当に最後となる。2017年の時のように復活に関する予告はない。
セローがこの選択を余儀なくされたのは、排ガス規制に加えて、ABSの義務化が足かせになったからだ。軽量コンパクトをよしとするトレールモデルに、あれこれと追加して生き長らえさせるのは得策でなく、ならばまったく新しいモデルで未来を見据えたほうが現実的だろう。
これとまったく同じ条件がSRにも当てはまり、そこに抜け道はない。継続生産車の場合、ABS義務化が適用されるのは、2021年10月からだ。そして1月21日、ついに「SR400ファイナルエディション」が正式に発表され、花道を飾ることとなった。
KTMやハスクバーナ、ロイヤルエンフィールドには素晴らしいビッグシングルが存在し、ホンダは海外で発表したニューモデル、ハイネス350(350cc空冷単気筒)を日本へ導入すると言われている。無邪気に期待できないものの、SRほどメーカーとショップとユーザーが三位一体となって盛り立ててきたモデルはない。なんらかのカタチで、そのDNAが継承されることを望みたい。