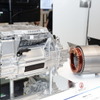ボッシュの日本法人は、昨年より運用している神奈川県横浜市都筑区の新社屋にて、定例の年次記者会見を行った。
まずクリスチャン・メッカー代表取締役社長が登壇し、2024年の日本国内における自動車生産台数は前年比8.5%減と、市場環境の厳しさが増しているという認識を示した。それでも昨年の日本国内における第三者連結売上高を約4280億円(約26億ユーロ超)とし、前年比+1%という僅かな伸びながらコロナ禍以来、3期連続で最高記録を更新できたことを好材料視しつつ、日本市場へのコミットメントを引き続き強めることを強調した。
地域や大学との連携強める
日本での事業を重視する姿勢として、モーターサイクル&パワースポーツ事業部が設立10周年を迎えたこと、さらにはボッシュカフェ1886やボッシュホールを新設した新社屋を通じて、都筑区や横浜国立大学と連携し、地域密着型の事業運営を挙げた。都筑区とは地域活性化に関する包括連携協定を結び、ボッシュホールにおける講演や様々のカルチャーイベントなどの運営の場を、パブリックに提供する。また横浜国立大学とは産学提携のひとつのカタチとして、機械工学系の研究室を対象にフルードパワートレーニングラボを開設。具体的には、プログラミングや電子制御などの情報工学分野に重きを置きやすい昨今の大学生の傾向を鑑み、油圧やアクチュエーターの実験機器を提供してリアルな制御エクササイズを学習の課題としてもらうことで、実際的な学びの経験機会を提供するというのだ。
会見後にプロジェクト担当者に聞いたところでは、「将来的に学生がエンジニアになって、当社の機器を購入してくれたらという青写真は無論ゼロではありません。でもそうした長期的な見通しより、制御やプログラミングをバーチャルだけでないところで動かしてもらう、油圧やフルードパワーでアウトプットするところまで一気通貫に体験してもらうことで、興味の幅を広げてもらうこと」こそが、主たる目的と語る。
「日本主導のテクノロジーが形になり始めている」
ボッシュ日本法人は研究開発についても地域密着型の姿勢を掲げている。OEMの多い日本においては、グローバルの従業員数に占める20%よりも、さらに多い25%が研究開発職に従事しており、日本主導のテクノロジーが形になり始めていると、西村直史取締役副社長は強調する。














![トランプ関税に「ジタバタしない」姿勢のトヨタも、米国市場で7月1日から値上げ[新聞ウォッチ]](/imgs/p/4r55aI4hIlVwLYFoZ_B1XH5Ok0DTQkNERUZH/2120124.jpg)