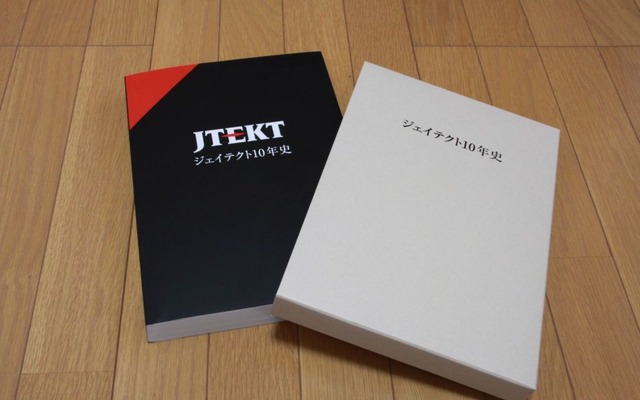『ジェイテクト10年史』
ジェイテクト社史編纂委員会 編纂
ジェイテクト発行
今回の書評はちょっと変わった書籍を取り上げる。変わったというのは、書店などに流通する書籍ではなく、いわゆる「社史」という内部的な書籍だからだ。基本的に会社の関係者、取引先などしか入手できないものとなるが、社史というものがどういう内容なのかの一例を紹介する意味でも取り上げる。
ジェイテクトの設立は2006年。会社として丸10年を向かえ、この社史が編纂されたわけだが、全編で400ページを超える超大作となっている。判型もA4サイズと大型だ。余談になるが、通常書店に流通させる書籍でA4正寸というのは多くない。理由はさまざまなだが、まず重く大きい本は流通で敬遠されがちだ。一度に多くを運べないからだ。用紙代、印刷費含めて総じてコストがかかる。高くても売れる、サイズに必然がある(美術書、図鑑など)ものならばよいが、そうでなければ文庫サイズ、B5、B6 (またはその変形サイズ)、四六判、菊判といったサイズになるのが普通だ。
社史の場合、部数は限定しやすく、一般的な書籍や雑誌の流通は考えなくてよい。いまはオンデマンド印刷のような方法もあるので、製本も少部数から可能だ。企画、編纂側の都合で自由な形態がとれるようになったからこその判型といえる。
そのおかげもあって、膨大な同社の歴史、技術、製品、工場など大判のカラー印刷で見やすい構成になっている。
ところで、設立10年の企業の歴史で400ページもの書籍が埋まるものなのだろうか。という疑問が湧く。ジェイテクトの前身をしらなければそのような疑問も無理もないが、同社は、光洋精工と豊田工機が合併して作られた会社だ。ご存じの読者もいるだろうが、光洋精工は1921年創業のベアリング等精密部品のメーカー。豊田工機は1941年にトヨタ自動車工業(当時)から分離独立した工作機械メーカーだ。
この2社は、2002年にトヨタ自動車、デンソーを加えたファーべスという会社を共同で設立し、電動パワーステアリングの開発・製造を始めた。この協業がきっかけとなり2006年、両者が合併しジェイテクトが生まれた。
「10年史」は大きく3部構成となっているが、このうち第2部までは光洋精工と豊田工機の歴史や製品技術についての話が並行して章ごとにまとめられている。第3部からがジェイテクト単体での話となっている。その第3部には「特別対談」として両社の役員が合併までの道のりを振り返る対談記事が掲載されているのだが、ファーべス設立の話や、合併時にお互いが気にしたことなども赤裸々に語られていて興味深い。
その中には「ジェイテクト(JTEKT)」という社名の由来について語られていた。市販書籍の場合、書評であまりネタばらしをするのははばかられるが、一般に流通しない社史なので、簡単に紹介する。
当時の両首脳は「銀行みたいに何社も名前をくっつけることはしたくなかった」とし、あえて両社の名前とは関係ない名前を考えた。JはJapanの意味。テクトはギリシャ語の「技の秀でた者」という意味だそうだ。そして、豊田工機のT、光洋精工のKも入っているのでJTEKTに決めたという。