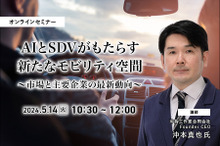ボッシュは今年1月のCES 2024で、同社のテクノロジーがいかに生活を、そしてサステナビリティを向上させられるか、オフィスビルディング、家庭、モビリティでの事例にについてプレゼンテーションを行った。車両が帰宅中のドライバーの疲れ具合を検知して家にあるコネクテッドコーヒーメーカーが事前にカプチーノを用意したり、自動バレーパーキングと同時にステレオカメラのついた充電プラグが自動的に車両に繋がり充電を完了したり、未来を示した興味深いデモがあった。
ロバート・ボッシュGmbH取締役会メンバー/ボッシュ モビリティ事業セクター統括部門長のマルクス・ハイン氏にモビリティに関するインタビューを行い、ソフトウェアデファインドビークル(Software Defined Vehicle、SDV)という概念をボッシュがどう捉え、どのような顧客価値を提供しようとしているのか、さらに電動化と自動運転の進化にどのように対応しようとしているのか、話を聞いた。
SDVのベースとなるもの
---:まず、ソフトウェアデファインドビークル(SDV)という言葉は自動車業界ではよく知られていますが、各社によってイメージが異なり、ハードウェアを主に考える企業もあればソフトウェアで実現するものと考える企業もあるようです。SDVを定義する際にどのような観点を持っていて、どのようなソリューションを業界に提供する予定ですか?
マルクス・ハイン氏(以下敬称略):良い質問ですね、しかし非常に広い質問です。まず、車両アーキテクチャについて触れたいと思います。ご存知のようにこれは車両の基盤であり、私の見解では、完全にソフトウェアデファインドな車両を実現するには、ソフトウェアを車両に導入できるようにするアーキテクチャが必要です。私たちは開発作業の大部分をこれに費やしています。
ブースでご覧いただいている例として、インフォテインメントシステムなどを1つのシステムオンチップ(SoC)に統合するというものです。さらにこれは、高性能コンピューターを実行するために必要なソフトウェアフレームワークと密接に関連しており、インフォテインメントやその他のドメインを処理しています。私の見解ではこれが2025年以降主流の開発形態になるでしょう。すなわち、ほとんどのOEMが3~5台の高性能コンピュータと、いくつかのゾーンコンピュータと、少数の従来からのECUで構成されるアーキテクチャを採用するようになると想定しています。
ソフトウェアをアップデートし続けなければならない理由
ハイン:重要なのは、提供するソフトウェアアーキテクチャによってコンピュータ間の連携がうまく機能しなければならないということです。ソフトウェアアーキテクチャの重要な点は、常にメンテナンスする必要があることです。一度作って終わりというわけにはいきません。今後、基本的に私たちのアーキテクチャの支配的な部分を占めることになるソフトウェアを継続的にメンテナンスする必要があります。
ただし、車両に機能を導入するにあたって、例えば運転中ドライバーに目立つ建物を知らせるような車両の安全性には関係ない機能と、車両の性能(ブレーキ、ステアリングなど)を左右する安全上重要な機能のどちらを対象とするかを考慮する必要があります。そしてSDVにおいても、安全上重要な機能はすべて本当に安全であり続けていることをわたしたちは保証する必要があります。これはわたしたちが追求する目的の一つであり、スマートフォンと車両の違いです。快適で楽しくあることが求められますが、安全でなければ意味がありません。
---:ボッシュにおけるSDVの強みは、機能安全、すなわちブレーキのような車両の安全にとって重要な機能への適応力にあるという理解で良いでしょうか。
ハイン:その通りです。ボッシュのソリューションの多くは安全性が重要で、リアルタイムデータが必要であり、車両安全の検証や認証に欠かせないため、私たちはそこに大きな労力を注いでいます。しかし、快適性や楽しさを向上させる機能も提供しており、これも私たちの取り組みに含まれています。ただし、安全性が重要な機能はすべて安全であることを徹底しています。
ソフトウェアとハードウェアの分離
ハイン:また、新しい機能を実装しながらも、ソフトウェアとハードウェアを分離するよう努めています。良い例として車両モーション管理が挙げられます。以前は、ステアリング、ブレーキ、パワートレイン用のソフトウェアが内包された完全なメカトロニクスシステムを開発していました。現在は、ソフトウェア機能のみを販売しており、そのソフトウェアはボッシュのハードウェアだけでなく他社のハードウェアでも使用できるようになっています。そのためには、ハードウェアとソフトウェアを抽象化するためのミドルウェアが必要です。
---:ということは、他のサプライヤーにソフトウェアのみを提供することも考えているのですか?