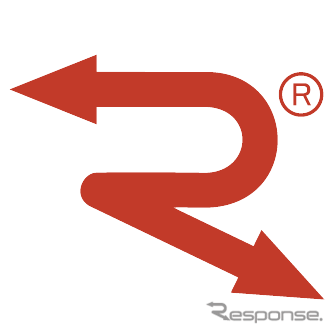サーキット走行を楽しむとなるとクルマの冷却対策は必須。そこでラジエーター交換はやはりしなければならないのだろうか。正しい冷却対策でクルマを壊さずにサーキット走行を楽しみたい。
◆サーキット走行をするならラジエーター交換は必須?
愛車でサーキットを走る走行会やスポーツ走行という楽しみ方がある。近年、合法的に全開走行ができ、リスクの低いサーキット走行は人気で、趣味としてサーキットを走る人は確実に増えている。
そんなサーキット走行を楽しむに当たって必須と言えるのが冷却対策である。それをきっちりとしていなければ、クルマを壊してしまう可能性が高いのだ。
SUPER GTやスーパー耐久などのレースでは、1回の走行で数時間連続で走るのは当たり前である。しかし、実はそれは並大抵のことではない。レーシングカーは真夏に連続走行できるようにつくられている。レーシングカーの凄さは速さでもあるが、実は連続で走って壊れないように作ってあることが凄いことなのである。
現在FIA GT規格という統一規格があり、GT3車両は約1億円。GT4車両は約3500万円という途方もない金額。だが、市販車をベースにあの速さを手に入れることは1周のみであれば可能だが、連続走行できる熱対策を施したうえであの速さで、その値段を実現しようと思ったらかなり難しい。それほどのことなのだ。
では、市販車で趣味でサーキット走行を楽しむ時にラジエーター交換が必要なのか。それはケース・バイ・ケースだが、結論から言えば、現代のクルマでは交換が必要になることは実は少ない。
日産『シルビア』S13/14/15や『スカイラインGT-R』R32/33/34、三菱「ランエボ」1~9、スバル『インプレッサ』GDBなどでは、サーキット走行を楽しむのであればラジエーター交換は必須だった。純正ラジエーターではあっという間に水温が100度を超えて際限なく上がってしまうのでは!? というくらい水温が上がってしまう。水量が多い厚みのあるラジエーターにしたりすることが定番だった。
だが、最近ではその常識が変わってきている。トヨタ『86』/スバル『BRZ』を例に取ると、水温は100度近くで安定するように設計されていてサーキット走行でもなかなかそこから温度が上がることがない。ラジエーター自体はかなり薄いものだが、それだけ走行風が抜けて熱を奪いやすいように設計されているようだ。十分なキャパシティがあるので、水冷式オイルクーラーを装着して、エンジンオイルの熱を冷却水で奪うようにしてもまず水温は上がっていかない。100度前後でビシッと安定してくれるのだ。
◆車体と走行シーンに合わせたチョイスが鍵を握る
このようにここ10年のクルマではエンジン冷却水の放熱キャパシティが高くなっている。それはラジエーター自体の進化もあるし、これまでよりも高い温度で水温を安定させることで燃焼効率をアップさせようという狙いがあり、意図的に高い温度で安定するようにしている。その影響かキャパシティ自体は十分であることが多いのだ。
むしろラジエーターをアフターパーツにすると、厚みを増して水量を増やしていることが多いので、オーバーハングが重くなりがち。意外とボディの先端なのでその影響は大きく、クルマの動きがもっさりとしやすい。
どうしても水温が上がってしまうというのでなければ、純正ラジエーターで十分ということも多いのだ。
だが、本格的に真夏に連続走行をするとか、ターボエンジンで大幅にパワーアップするとなると、純正ラジエーターでは放熱量が足りず、水温がグイグイと上がっていってしまうことも珍しくない。
そんなときにはアフターパーツのラジエーターの出番である。ここで注目したいのは厚みがあることが熱に強くなるわけではないということ。厚みがあるラジエーターは水量が増えるので、全体のキャパシティが上がる。しかし、重くなりがち。しかも、厚みがあると走行風は抜けにくくなり、熱交換の効率としては悪くなる。薄いラジエーターで走行風をバンバン入れてバンバン抜いたほうが熱交換の効率が良いこともある。
ハイスピードなコースで風速の高い風がバンバン当たるなら厚みのあるラジエーターもありだが、ミニサーキットなどで車速が低いなら薄めのラジエーターで風がよく抜けたほうが水温を下げやすいこともある。
その風が抜ける観点から言えば、ラジエーター後方に風が抜けるスペースがあるかどうかも重要。ボンネットに風抜きダクトがあると効率よく水温を下げられることがある。エンジンルームからどう風が抜けるかも考えてボンネットにしたり、ダクト付きフェンダーにすることで水温を下げることもできるのだ。