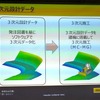土木建設業界では、2020年に向けて人材不足が懸念されている。国土交通省は、土木建設現場における生産性向上と死亡事故ゼロの実現に向けて『i-Construction』を推進している。i-Constructionとは、ICT技術によって建設現場の生産性を向上させる取り組みだ。
そんななか、日本キャタピラーでは、i-Constructionの認知拡大と、ICT建設機械の普及のため、建設工事事業者向けの説明会を随時実施している。宮城県岩沼市の日本キャタピラーICTセンターで取材した。
プレゼンテーションに登壇した日本キャタピラー 東北支社営業部の佐々木一平氏は、「今後は労働力不足が予想されており、2025年で130万人不足する見込み。i-Constructionへの対応によって、生産性向上はもちろん、ICT導入による雇用機会の拡大を実現できる」と説明した。
建設現場のプロセスを大雑把に分けると、測量→設計→施工→検査と続く。i-Construstionとは、これらのプロセスをICT技術によって生産性の向上を目指す取り組みである。具体的に言うと以下のようになる。
測量:ドローンによる写真データによって3次元測量
設計:測量データを3次元設計データに変換
施工:設計データによってICT建設機械を自動制御し施工を実施
検査:ICT建設機械の稼働ログによって検査を実施
国土交通省は、競争領域と協調領域を分けることで業界の健全な進化発展を促している。例えば、上記でポイントとなる3次元設計データにっついては、業界共通のフォーマットを制定しており、事業者間の健全な競争を促進する環境づくりを意識している。
ICT建設機械によるデモンストレーションでは、3次元設計データを取り込んだ油圧ショベルやブルドーザーが、自動制御によって正確な施工をスムーズに実施する様子が披露された。
建設現場のICT化によって、生産性の向上がもたらされるのは事実であろう。いっぽうで、建設事業者にとっては、ICT化するための人的、設備的な投資が必要なのも事実だ。特に、土木建築企業は9割以上が社員数10名以下の小規模な企業で占められている。
日本キャタピラーの取り組みは、自社のICT建設機械のアピールはもちろんだが、近い将来の人材不足を見据えたうえで、ICT化による建設事業の雇用のすそ野の広がり、高付加価値化に向けた取り組みの重要性もアピールするものだ。
〈取材協力 日本キャタピラー〉