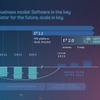フォルクスワーゲンは7月13日、2030年へ向けたグループの中期的戦略を「ニュー・オート 来る世代のためのモビリティ」と題し、オンラインのカンファレンス形式で発表した。基本的には電動化と自動運転を将来的なキーテクノロジーと位置づけることを再確認させる内容だが、そのアウトラインや具体的な柱となるものに、いくつか新しい要素が認められる。
英語の「NEW AUTO」に込めた思い
 VW ヘルベルト・ディースCEO
VW ヘルベルト・ディースCEO
まず「ニュー・オート(NEW AUTO)」という呼称についてだが、念のためドイツ語の公式サイトもあたったところ「ノイエ・アウト」ではなく英語のまま「ニュー・オート」だった。一時期のVWは「DAS AUTO(ダス・アウト=ザ・カーの意)」というドイツ語の定冠詞つきのキャッチコピーを掲げ、自らを中心に位置づけるような傲慢さが逆に頼もしくもあった。あの頃の面影と多少リンクしつつも、従来と異なる新しい章へ、新しいページをめくったことを思わせる。
冒頭、VWのヘルベルト・ディースCEOのキーノート・スピーチで、早々に示されたことだが、ICE(内燃機関)モデルの販売は向こう10年で20%以上の減少が見込まれる事を、早々に宣言。だが図表で示された、収益割合の中での減少幅は穏やかで、逆にEVの販売に占める割合は2030年に向かって増していくが、ICEと同程度のボリュームが見込まれるという。つまり2030年に半々、という見立てだ。
またディースCEOが3本目の収益の柱と見込むのはソフトウェアとサービス分野だ。個人モビリティとしての移動サービスにも言及しており、カーシェアとウーバーとタクシーがすべて自動運転とネットワークの元にまとめられ、スマートフォンのアプリが窓口となるようなイメージだった。加えてバッテリーに含まれる資源物資の再利用にも言及しており、EVでの一次使用の後に、家庭などで備蓄電源としての二次使用、それからリサイクルに回すというバリュー・チェーンを構築し、EV事業の収益性を高める。
EVそしてソフトウェアと付随するサービスを合わせると、VWによれば、今日の自動車業界の約200兆ユーロという市場規模は、4年後に300兆ユーロ、2030年に500兆ユーロが見込まれる。それはスマートフォン市場の10倍の規模で、テック業界のプレーヤーが自動車に参入したがる理由であると、ディ―スCEOは説明する。
以上がアウトラインだが、以下はキーノートで言及され、各担当者が補強した要素を箇条書きで挙げてみよう。
ブランド・ポートフォリオ
 アウディ Q7 ベースの自動運転プロトタイプ車
アウディ Q7 ベースの自動運転プロトタイプ車
プレミアム・セグメントにおいても、アウディが高度な効率によるレベル4の電動化プラットフォームで先行開発的な役割を果たす。ベントレーはそれを利して洗練されたラグジュアリーEVを、ランボルギーニとドゥカティはこれらのテクノロジーによってポートフォリオのテコ入れを図る。ソフトウェアやサービスによって各プレミアム・ブランド自体の差別化は進む。
VWはボリュームを追求。先進的なプラットフォームで市場でもっとも分かりやすいEVポートフォリオを展開し、『ID.3』~『ID.6』、『ID.Buzz』を投入してEVにおけるリーダーを目指す。さらに将来的なハイテクノロジー・プロジェクト「トリニティ」によって、手の届く価格のレベル4かつEVプラットフォームを量販セグメントに投入し、その規模とテクノロジーをクプラ、シュコダに供給かつ共有する。
ポルシェは高度な独立性を保ち、インダストリアル面でもグループに一体化しており、テクノロジーの独自性でグループに貢献しつつ、その製造スケールを享受し続ける。2030年までに販売の80%をEVに。
先日、リマックとのジョイントベンチャーを発表したブガッティについて言及はなかったが、ブガッティ・リマックの資本の45%、そしてその母体となるリマック・グループの24%をポルシェが握っていることは既報の通りだ。
新メカトロニック・プラットフォーム「SSP」
 新メカトロニクス・プラットフォーム「SSP」についての言及も
新メカトロニクス・プラットフォーム「SSP」についての言及も
2026年より、VWグループは次世代テクノロジーの集約としてSSP(スケーラブル・システムズ・プラットフォーム)というメカトロニック・プラットフォームを開発。メカトロニックとは聞きなれない言葉だが、機械電気情報工学のことで、プログラミングから電子制御、メカニズムの設計や作動まで同時に統合する分野ということ。いわゆる車台や共有コンポーネント群を指すプラットフォームとは一線を画す。
SSPはMQB、MEB、MLB、PPEといったすべての既存プラットフォームに対して、ひとつのアーキテクチャとして補強する。エントリーレベルからトップレンジまで、競争力を備え、先鋭的かつ比類ない規模のアーキテクチャとして、E-プロダクトのポートフォリオ全体、85kWh~850kWhまでカバーする。100%電動車用で自動運転かつグループ内の全ブランドに対応。メカトロニック・プラットフォーム開発能力と速度を向上させるため、8億ユーロを投資する。
様々なサイズのプラットフォームに異なるモジュールを組み合わせることで、各ブランドは差別化を図ることができる。2025年にアウディの『アルテミス』がSSPモジュールの枢要部を初めて用いる。翌年にはVWが『トリニティ』で、SSPベースによる初のモデルを通じて、このテクノロジーを量販セグメントに投入する。
ソフトウェアが自動運転の要となる
 VWグループのNEW AUTO戦略。かねてよりVWはソフトウェアの重要性を説いている。
VWグループのNEW AUTO戦略。かねてよりVWはソフトウェアの重要性を説いている。
VWはソフトウェアこそ自動運転の要と捉えている。今後の数年間で、グループ内のソフトウェア&テクノロジー会社であるCARIADは、新しいソフトウェア・アーキテクチャを開発し、グループ内全ブランドからシナジー効果を上げる。新たなソフトウェア・アーキテクチャこそが、循環的システムの画竜点睛で、プロダクトの全ライフサイクルを通じて顧客自身が主体でいられるソフトウェア・サービスを提供するという。
2030年までにVWグループは新しいソフトウェアに基づいた車を4000万台以上、全世界の路上に供給することで、業界でもっとも大きなリアルタイム・データを集約し、漸次的にプロダクトの改良に充てる。2025年までに自動車メーカーのインハウス開発によるソフトウェアは、現在の10%から60%に伸びる見込み。CARIADはグループの全ブランドと密に協業し、ソフトウェア・アーキテクチャは全グループ内のモビリティを変化させる。
バッテリーと急速充電
 VW ID.4
VW ID.4
2040年までに、世界の主要市場におけるVWグループの車両は、100%クライメート・ニュートラルになるという。そのカギを握るのが、バッテリーと充電インフラだ。
EVでもっともコストのかかるパーツはバッテリーだが、グループ内での修理やリサイクルによってグループ内部でバッテリー供給が可能になれば、劇的にコストは下がる。その中心的役割を果たすのが、2023年から予定されるVWが独自の統一フォーマットで揃えられたセルだ。それは単一種類のセルではなく、むしろ複数の異なるセルであるとの説明だが、グループ全体でスケールメリットを享受するのは同じ。今回はプレミアムと量販の各セグメントでの要件や特徴、使い分けや割合については、具体的に示されなかった。
e-モビリティ実現に向け、VWはパートナーシップによる充電インフラの拡大と、自動車を核とするエネルギーの循環システム構築を目指す。ここでは車両自体が、自立して移動できる、インテリジェントな電力バンクとなる。また素早く簡単な充電を可能にする充電インフラは、分かりやすいものでなければならないとする。
モビリティとソリューション「ロボ・タクシー・サービス」
より安全でよりインテリジェント、かつ自律的な個人モビリティを供給することが、グループの使命。フル自動運転によるモビリティ&トランスポート・サービスも、2030年のVWのビジネスモデルでは視野に入れる。この「ロボ・タクシー・サービス」は4層のレイヤーを必要とするそうで(1)予約プラットフォーム(2)車両フリート・オペレーション(3)自動運転車両(4)ヴァーチャル・ドライバー からなる。1は支払いや利用データが含まれるもっとも収益性の高いパートで、3の車両はID.Buzzがベースとなる。そして4はソフトウェアとしてかつてない複雑なものになるが、学習機能によってその運転能力を高め、収益も高まるという。
VWは、戦略的パートナーであるARGO AIと、自動運転シャトルカーのための無人システムの開発を進めており、ミュンヘンで先行プロジェクトとして初の自動運転バスをテストしている。他にもドイツの主要都市やアメリカ、中国でも同じ実験を行う。2030年までに欧州主要5か国でのMAAS市場は700億ドル規模と見込まれ、2025年に欧州で初の自動運転モビリティ・サービスを導入する予定という。
サステナビリティに対する投資
 フォルクスワーゲン
フォルクスワーゲン
2030年までにVWグループは、車両1台あたりのライフサイクルにおけるCO2フットプリントを、30%減らす。概算で1台あたりでいえば、今日50トンのところを34トンにまで減らす。2040年にはすべての主要マーケットでの販売をゼロ・エミッション車両に。2050年にはすべてのオペレーションがクライメート・ニュートラルであることを目指す。
このため2025年までに、将来的な開発投資として730億ユーロを投じる。ICEのビジネスについては、財務管理部門の主導によって、パワートレインのポートフォリオやモデルを3分の1ほど減らし、よりよい価格とする。
欧州と中国とアメリカは、2030年もVWの主要マーケットであり続ける。
かくも、広範囲にわたる内容であるがゆえ、どの項目が日本のカスタマーに影響してくるか、実感が沸きにくいところだと思うが、エネルギーミックスよりは電動化への選択と集中によるロードマップを、VWはスケールメリットをレバレッジに進めていくようだ。