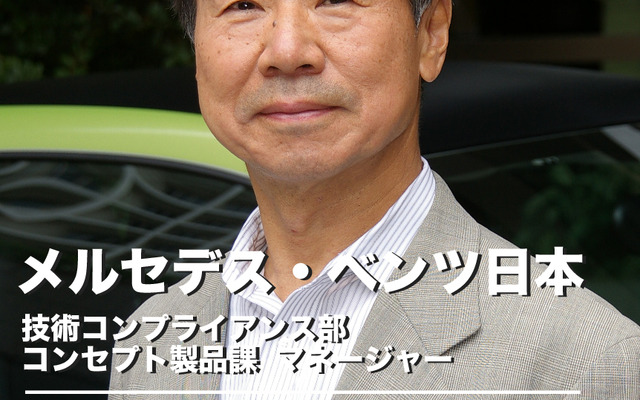メルセデス・ベンツ日本は、小型車スマート『フォーツー』の電気自動車(EV)モデル『フォーツー エレクトリックドライブ』の予約受付を開始した。ダイムラーはこのEVの導入にあたり日本国内でも実証実験を実施するなど、車両の電動化に向けた世界的な取組みを行っている。
日本でのEVの実証実験などを手がけたメルセデス・ベンツ日本・技術コンプライアンス部コンセプト製品課の東條和吉マネージャーに、ダイムラーの環境対応や日本市場での戦略などについて聞いた。
----:ダイムラーの環境対応戦略をお聞かせください
東條:CO2と化石燃料。この点を考慮すると、エネルギー効率を上げるためにはコンベンショナルエンジンでは限度があります。技術革新していかなければいけない。つまり電気エネルギーを活用していくということです。電気にいくにあたっては燃料電池とバッテリーのEVがある。特に一次エネルギーを再生可能なエネルギーにすることで、かなりエネルギー消費量やCO2の排出を下げられる。そのための最終的なソリューションとして電気、“e-mobility”に取り組んで行くというのがダイムラーの戦略なんです。
----:現状では1つの技術に絞り込むのではなく、既存の内燃機関を始めハイブリッド車やEVなど様々な方式を提供していますね
東條:基本的に現在はコンベンショナルなエンジン。一足飛びに電気にいくことはできません。ダイムラーも2020年、2050年を見据えて電気化を進めていきます。でも、その途中としてはコンベンショナルなエンジンのみならず、ディーゼルハイブリッドとか、プラグインハイブリッド、レンジエクステンダーなど、多面的に取り組んで行くというスタンスです。
----:様々な段階を踏んでいくということですが、2020年や2050年時点の姿はどうなっていくのでしょうか
東條:2014年には燃料電池車を一般に販売します。日本では2025年には燃料電池自動車もプロフィッタブルになると予測していますが、ダイムラーは、もう少し前の段階で達成したいと考えています。
一方、EVは今年から量産車を出していきます。しばらくはフォーツー エレクトリックドライブになるとは思いますが、次のフルモデルチェンジ時にもEVを出して台数を拡大して行きます。2020年代にはターニングポイントがあるのではないでしょうか。
そして2050年には、ほとんど電動自動車にいかざるを得ないかなと思います。ただ課題はたくさんありますので、そういう点はクリアしていかなければいけないというのは事実だと思います。
----:日本でスマートEVの予約受付が始まりました。導入にあたっては日本でも実証実験を行いましたが、実証実験の結果が製品に反映されたものはありますか
東條:一番大きいのは中速域の加速です。0-100km/hが26.7秒かかっていたのが、11.5秒になりました。最高速度も100km/hから125km/hに向上しています。またモーターやバッテリー容量も少し上がり、よりクルマとして使いやすいものに改善されてきています。
----:日本で販売するスマートEVは急速充電に対応していませんが
東條:ダイムラーが持っているEVでいうと日本のチャデモ方式と考え方が違うので、急速充電には対応していません。そういうEVが日本で使えるかどうかを実証実験で検証しました。モニターの方には事前に急速充電が無いという話をしたところ心配だという反応でしたが、実際に使ってみると全然必要なかったということでした。
現実的に見れば、ゼロから100%までフルに充電することはほとんどありません。実際には満充電までそれほど時間かからないというフィードバックもありましたので、200Vであれば日本の中でもなんとかなるのではないか、急速充電が無くても売れるのではないかという判断を本社に伝えました。当然、急速充電への対応も本社に要望はしますが、世界的な基準の問題や日本での台数から、コストをかけて日本ユニークのものを造るという判断には至っていない、というところです。
----:EVの充電方式を巡っては様々規格がでていますが、ダイムラーのスタンスは
東條:現在はEVを売り出したばかり。ダイムラーもやるし、フォルクスワーゲンもBMWもやると言っています。でもインフラが世界中で違っているので、これはすぐには統合できない。今の段階では色んな方式をやってほしい。我々としては交流3相のものを日本でもやれないかと色んな方々にお話をしている最中です。違った方式にも対応できれば、確かに良いと思います。その中で淘汰していけばいいのではないかと考えています。
----:東日本大震災以降、日本ではEVから外部に給電する機能が注目されていますが
東條:スマートEVに給電機能はありませんが、ドイツの中でもグリッドとのコミュニケーションを含めて、ダイムラーとヨーロッパの電機メーカーと一緒に検討はしています。
----:ダイムラーとしても給電機能は必要と考えているのでしょうか
東條:ヨーロッパもアメリカもグリッドが弱かったりするので、これはやっぱり必然性として出てくるとは思います。家庭向け蓄電池として容量が1kwh程度のものが販売されていますが、それに比べるとEVのバッテリーは数日分の家庭用電源を賄える量を蓄えられるので、これを何かあった時に使うというのは当然だとは思います。
----:7月に開催されるEV Battery Japan 2012で、スマートEVの販売戦略の一環として「バッテリーリース」をおこなう意義について講演されますが
東條:日本では法規制や販売規模の点からすぐには実現できませんが、我々がヨーロッパでおこなっている『セール&ケア』という画期的な販売方法を紹介しようと考えています。この仕組みは、基本的にEVはバッテリー無しの状態、ドイツではグライダーといってますけど、そのグライダーをお客さんに販売します。一方、バッテリーは10年間、月々65ユーロで使用する契約を結んで、10年間毎年メインテナンスしてもらうというものです。そうすると毎年そのEVをディーラーに誘導することができますので、ディーラーにとってメリットがあるわけです。
----:ユーザー側のメリットは
東條:10年間バッテリーが保証されるということです。今、EV用のバッテリーを10年間保証している会社はありません。どの会社もバッテリーの寿命を実証試験したことがない。この大クエスチョンマークのものを10年間保証する。我々にとってのリスクはとても大きいですが、お客さんにとっては非常にメリットがあるものだと思います。
----:ダイムラーが考える次世代のモビリティの姿は
東條:使い勝手でいうと、大型車から小型車含めて燃料電池車が長距離、中距離移動をカバーしていきます。一方、エネルギー効率でいうとEVは、燃料電池車以上です。やはり水素を造るには手間もエネルギーもかかりますので、そういう点でいえばバッテリーの方が優れているといえます。ですから短距離の走行にはやっぱり小型車としてEVが使われるのではないでしょうか。
ただ走行距離が長くなったり重量が大きくなったりすると燃料電池車のコストパフォーマンスが上回るというのが現状の結果だと思います。ダイムラーでいえば、燃料電池車は大型の『Sクラス』や『Eクラス』、それからバスなど。スマートや小型車についてはEVという棲み分けになるのではないでしょうか。
東條マネージャーは、7月3日、4日に開催されるEVバッテリーに関するカンファレンスイベント「EV Battery Japan 2012」に登壇予定。スマート フォーツー エレクトリックドライブの紹介を中心に、ダイムラーの持続可能なモビリティ戦略について語る。
■EV Battery Japan 2012
会場:ヒルトン東京(新宿)
日程;7月3日(火)~4日(水)
http://www.evupdate.com/ev-battery-japan/jp-index.php