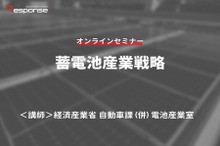次の社会を支える重要技術となる蓄電池技術は、今後、自動車産業と両輪となって日本経済を牽引する可能性を秘めている。まもなく開催予定の無料オンラインセミナー「蓄電池産業戦略」に登壇する経済産業省 製造産業局 自動車課 課長補佐(併)商務情報政策局 電池産業室 室長補佐の齋藤健氏に、セミナーの見どころを聞いた。
■セミナー概要
無料【オンラインセミナー】蓄電池産業戦略
開催日時:2022年12月23日(金)13:00~14:00
申込締切:2022年12月22日(木)正午
1.導入(蓄電地の重要性)
2.蓄電地の市場の拡大、シェア推移、各国の支援策
3.蓄電地のサプライチェーン
4.蓄電池産業戦略における基本的な考え方、全体像、目標
5.今後の取組 など
6.質疑応答
セミナーの詳細はこちらから
リチウムイオンバッテリー生産への支援を強化
--:現在の蓄電池は液系のリチウムイオンが主流ですが、今後どのように蓄電池技術を支援していくのでしょうか。
齋藤:当面は液系のリチウムイオン電池が主流になるのではないかと見ていますが、一方で我々としては、次世代の蓄電池として全固体リチウムイオン電池等についても、自動車OEMの将来的な競争力を確保する観点から研究開発支援の必要性を感じています。
例えば、NEDOプロジェクトの中のSOLiD-EVといったプロジェクトや、グリーンイノベーション基金を活用し、この全固体電池といった次世代蓄電池の研究開発を政府としても支援しています。日本の研究開発がもともとはかなりリードしていたのですが、最近は中国の特許取得件数が非常に増えるなど、徐々に他国に差を詰められているという状況です。
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](https://response.jp/imgs/fill2/1830574.jpg) 経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
政府による支援については、これは電池の分野に限らないことですが、例えば増産設備の導入などの部分はこれまで個社でやっていただくことが多く、政府の支援政策が少ないということがありました。そのような中で、他国が政府の強力な支援を背景に液系のリチウムイオン電池の技術が日本に追いつき、コスト面においても国際競争力をつけてきているという状況で、世界的に投資競争が激化しています。
それに加えて、少し前までは2020年ごろにできるのではないかといわれていた全固体電池も、まだすぐには市場に投入できない状況であるため、液系のリチウムイオン電池の市場は当面続く見込みであると考えています。このままでは全固体の実用化に至る前に、液系のリチウムイオン電池を作っている段階で、市場から撤退せざるをえない状況になるという懸念があります。
今後の方向性として、液系リチウムイオン電池の製造基盤を強化するための大規模投資への支援を行ったり、海外展開も戦略的に行い、グローバルプレゼンスを確保しようと考えています。
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](https://response.jp/imgs/fill2/1830575.jpg) 経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]また、引き続き全固体電池などの次世代電池実用化に向けて、技術開発を進めていくということに併せ、人材育成や、リユース・リサイクルの観点などの環境整備も同時に進めていくという基本的な戦略を考えています。
具体的な取り組みと全体像については、蓄電池や蓄電池材料の国内製造基盤確立のための政策パッケージや、上流資源の確保に向けた支援スキームの強化、次世代技術開発の支援、市場の創出などを行います。
さらに、電動車の普及、促進のためのCEV補助金などで市場の創出を促していきます。また、環境整備については、蓄電池関連メーカーが関西圏に多く、大学の研究も関西で盛んである観点から、まずは関西を中心とした、人材育成のコンソーシアムを立ち上げました。
1st Targetとして、国内製造能力については、遅くとも2030年までに蓄電池・材料の国内製造基盤の150GWhの確立を目標とします。もともと、グリーン成長戦略の中では車載用蓄電池にのみ限定して、2030年までの早期に100GWhの確立と記載していたのですが、定置用も含めて全体で150GWhと、少し引き上げる形で今年の8月にこの目標設定を掲げています。
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](https://response.jp/imgs/fill2/1830576.jpg) 経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]これは国内製造基盤についてなのですが、グローバル市場では、日系の企業全体で2030年までに600GWhの生産能力確保を目標として掲げています。
また、2030年ごろに全固体電池の本格実用化を目指し、引き続き研究開発をしていくことも目標としています。
--:リチウムイオン電池の増産は、数千億から兆円単位の投資が生じることもあり、いち企業でまかなえるだけの規模を超えています。この1st Targetの支援というのは、実際にそのような資金的支援も含むということなのでしょうか?
齋藤:はい。令和4年度の補正予算として、3316億円の用意をしています。
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](https://response.jp/imgs/fill2/1830577.jpg) 経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]実は令和3年度の補正予算でも1000億円を措置し、すでに投資支援の補助金を実施しています。この補助金は今年の3月から4月にかけて公募を行い、6月に一次採択結果を公表しています。二次公募についても、8月の下旬から10月の上旬にかけて公募をしていて、現在審査中です。12月中旬までには採択企業も決まり、公表ができると思います。
まずはそのような形で、昨年から1年かけて1000億円を製造基盤確保の支援にあてています。令和4年の補正予算では、昨年は1,000億円であったところを3300億円規模の予算を確保し、申請のスキームは異なりますが大枠は同じような制度で、引き続き継続的な立地支援をしていきます。
--:こちらは、主に国内のリチウムイオンバッテリー工場への支援ということでしょうか?
齋藤:はい。蓄電池や部素材である正極材、負極材、セパレーター、電解液などの製造設備や技術開発が対象です。
--:一方でこの2nd Targetにあるグローバルプレゼンスの確保というのは、具体的にどのような事業活動に対する支援ということになるのでしょうか?
齋藤:JBICやNEXIからのファイナンス支援や、ルール形成、国際標準化戦略といった部分を国としてバックアップし、支援していくという考えです。
他国との協力や、GtoGでの対話など、例えば欧州でバッテリー規則というようなルールが議論されている中で、我々としても欧州側と政府間で議論を行うなど、日本の企業が活動しやすくなるような環境整備は政府としてもできる限りのことをやっていくという考えです。
--:これは今後どの程度の時間軸を考えているのでしょうか。
齋藤:具体的な施策は、基本的に2030年ごろを見据えたものが多いです。目標として掲げているのも、まずは2030年までに国内であれば150GWh、海外であれば600GWhの製造能力確保ですから、2030年というのが時間軸としての1つの目印であると思っています。
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](https://response.jp/imgs/fill2/1830578.jpg) 経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]
経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]齋藤氏が登壇する無料のオンラインセミナーは12月23日開催。申込締切は22日正午まで。詳細・お申込はこちら。

![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/thumb_h2/1830545.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830545.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830574.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830575.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830576.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830577.jpg)
![経済産業省に聞く蓄電池産業戦略…経済産業省 自動車課 齋藤健氏[インタビュー]](/imgs/sq_m_l1/1830578.jpg)