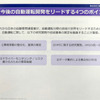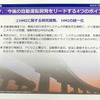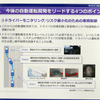日本の自動車産業が、自動運転分野の技術で世界をリードするためにはどうすればいいのか? 三菱総合研究所は11月11日、「自動運転を巡る世界の自動車業界の覇権は」と題したプレゼンテーションを実施した。
講演したのは、三菱総合研究所主席研究員でスマートインフラグループグループリーダーの杉浦孝明氏。杉浦氏は、日本の自動車産業が、自動運転分野の技術で世界をリードするために、以下の4つの領域の強化が不可欠だと語った。
1. 車両挙動の整合化、基準の策定
2. HMIに関する研究開発、HMIの統一化
3. ドライバーモニタリング/リスク最小化のための車両制御
4. データ集約による集合知の形成
まず1つめの領域、「車両挙動の整合化、基準の策定」について。これについて杉浦氏は「例えば大型トラックと乗用車では、同じACCを利用した場合でも制動距離が大きく違う」ことから、基準が必要だと説いた。
「10年後には、大都市圏の半分の車両にACCが搭載されている状況」というなか、大型トラックの後ろを走行する場合は、通常の2倍の車間距離を取る、などの基準づくりを急ぐべきという内容だ。
2つ目の「HMIに関する研究開発、HMIの統一化」について。自動運転において、車両の運転状況を伝えるHMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)を統一すべきという提言である。
例えば、「運転中にスピードを確認する場合、スピードメーターを見るが、これは「スピードメーターとはこういうもの」という共通認識があるため、誰でも惑うことなく情報を得ることができる」。
「自動運転においても、車が今どのような状況で運行されているのか、利用者が惑うことなく瞬時に理解できるHMIを構築する必要がある」とした。
3点目の「ドライバーモニタリング/リスク最小化のための車両制御」について。杉浦氏いわく「運転支援サービスが進化するにつれ、ドライバーの運転介在度が低くなる。いざという時に、ドライバーに確実に運転行為を受け渡すため、ドライバーがいまどのような状態にあるのか、居眠りしていないか、わき見をしていないか、きちんと着座しているか、倒れこんでいないか、モニタリングすることが必須である」。
4点目の「データ集約による集合知の形成」については、「ここは道が狭くて危ない」「この辺はいつも高齢者が多い」など、個人の経験知を集約し、活用することが重要である」とした。
「これら4つの領域は、今まさに世界中でしのぎを削っている部分。日本の自動運転産業の発展のためには、ここで存在感を出すことがとても重要だ」と力説した。